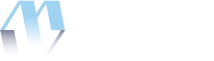3Dプリンターの材料の多様化と活用シーンの拡大
製造業に属する様々な業界において、3Dプリンターの活用が急拡大しています。その要因のひとつに、3Dプリンターでの造形に利用可能な材料の多様化が挙がります。それまで特定の樹脂材料だけしか利用できなかった3Dプリンターで、金属やセラミックスをはじめとする多彩な材料を扱えるようになったことで、様々な工業製品の多様な開発・生産の要件に応えることができるようになりました。
この記事では、3Dプリンターで利用可能な材料を網羅的に挙げて、それぞれの応用適性を紹介します。さらに、多様な材料を利用可能になったことで、3Dプリンターの応用分野と利用シーンが拡大し、様々な産業にイノベーションを生み出す可能性があることを、事例を挙げて解説します。
利用可能な材料の多様化で、3Dプリンターの応用範囲が急拡大
利用可能な材料の多様化で、3Dプリンターの応用範囲が急拡大
3Dプリンターでの造形に利用できる材料が急激に多様化
3Dプリンターを使って作成可能なモノの種類とその利用シーンが急拡大しています。実用化された当初、製造業での主な用途は、試作や意匠デザインの確認などが中心でした。CADで設計したモノの形状を忠実に再現することはできたが、そのまま製品に適用する機能・性能・品質は実現できなかったからです。これが現在では、エンドユーザーが使う製品に組み込まれる部品の量産や生産工程などで利用する治工具の製作、保守・修理・運用(MRO)部品の製作などにも適用されるようになりました(図1)。
図1 利用可能な材料の多様化で、製造業での3Dプリンター利用シーンが拡大
さらに、品質や信頼性に対する要求が特に厳しい自動車用部品や医療機器などの量産に利用される例も散見されます。設計データを迅速かつ忠実に具現化できる3Dプリンター固有の特長を生かして、切削や射出など従来成形技術では実現できない形状の部品製作や消費者ニーズに合わせたカスタム部品の作成などに有効活用できる環境が整っています。
複合材料の利用や複数種類の併用も可能に
実用化したばかりの時点では、扱える材料は、熱可塑性や光硬化性など3Dプリンターで加工しやすい特定の樹脂材料だけでした。これが現在では、従来技術で加工できる材料のほとんどが適用できるようになりました。
適用材料が多様化したことで、強度、耐熱性、柔軟性、電気的特性、耐薬品性、生体適合性といった機能を持つ高度な部品やデバイスを実現可能になりました。現在では、3Dプリンターで造形した部品は、航空宇宙、医療、自動車、エレクトロニクスといった分野の製品で求められる実用的要求水準を満たすだけでなく、3Dプリンターでなければ実現できない新たな価値を持つアプリケーションを開拓できるようにもなってきています。
RX Japan 合同会社では、日本最大級の製造業の展示会「ものづくり ワールド」を東京で行うほか、大阪・名古屋・福岡でも開催しております。
展示会場では、製造業の最先端事例や設計開発の最前線の話題が学べる併催セミナーも開催しています。
来場だけでなく展示会への出展も受け付けております。気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
●出展・来場に関する情報はこちら
樹脂から金属やセラミックスまで、機械部品の材料はほぼ網羅
樹脂から金属やセラミックスまで、機械部品の材料はほぼ網羅
材料と加工法、双方の技術を擦り合わせ開発
自動車部品の製作では、ボディに向けた大型部品は鋼板のプレス加工、エンジンを構成する精密部品は金属塊の切削加工、ダッシュボードは樹脂の射出成形とそれぞれ個別の加工法で作成しています。
一般に、加工対象の材料と加工技術の組み合わせは大まかに対応しています。例えば、樹脂など液状化できる材料は射出成形で加工することはできますが、金属材料には射出成形は適用できません。複数の加工法を適用可能な材料を対象にする際には、高精度な加工が求められる際には切削加工やレーザー加工などを、低コストでの大量生産が求められる場合にはプレス加工や鋳造などを適用するといった具合に、ワークの形状や要求条件に応じて加工法を使い分けます。
3Dプリンターを利用する際も同様です。3Dプリンターには特徴の異なる様々な造形方式があり、利用する材料に応じた方式の加工法を利用する必要があります(図2)。これまでにない材料を投入する際には、加工法に技術革新が求められる場合もあります。3Dプリンターが実用化して以降、現在に至るまで、材料開発と加工法の双方で技術開発が進んだことで多様な材料の適用が可能になりました。そして現在では、切削・射出・プレスといった従来技術では加工できなかった難加工材を使って、これまで実現できなかった形状・構造・機能を備えた部品やデバイスを3Dプリンターで生産できるようになりました。
図2 使用する材料によって、利用可能な造形法が定まっている
現在、3Dプリンティングで利用されている材料は、大別すると、樹脂(熱可塑性樹脂、光硬化性樹脂)、金属、セラミックス、複合材料、生体材料、そして導電性や絶縁性などの特定の機能を持つ機能性材料に分類されます。
そして、熱可塑性の樹脂材料は「熱溶解積層法(FDM)」「材料押出法(MEX)」で、硬化前が液状の光硬化性樹脂材料は「光造形法(SLA)」「液相光重合法(SLA)」「材料噴射法(MJT)」で、粉末状の金属材料やセラミックス材料は「選択的レーザー焼結法(SLS)」「粉末床溶解積層法(PBF)」「バインダージェット法」で、一部のワイヤー状や粉末状の金属材料は「指向性エネルギー堆積法(DED)」で造形します。
ここからは、現時点までに3Dプリンターで扱えるようになった材料を具体的に挙げ、対応する造形技術、および応用分野などを解説します。
造形技術の精度・生産性の向上が進む「樹脂材料」
樹脂材料には、多様な物性の物質が存在します。さらに、部品などを作る材料として取り扱いが比較的容易です。これらの理由を背景として、3Dプリンティングにおいて最も広く利用されています。3Dプリンター用の樹脂材料は、熱可塑性樹脂と光硬化性樹脂の2種類に大別できます。このうち、熱可塑性樹脂には、さらに以下のような多様な材料があります(図3)。
図3 3Dプリンターで利用可能な樹脂材料とその特徴、代表的応用
PLA
「ポリ乳酸(PLA)」は、トウモロコシなどを原料とする植物由来の環境にやさしい材料です。扱いやすい材料でもあるため、工業製品の意匠デザインの確認などに広く利用されています。
ABS
「アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)」は、優れた強度・耐衝撃性・耐熱性を備えながら後加工(研磨・塗装)が容易な材料です。機能確認用の試作品や治工具、最終製品向け部品の生産に用いられています。
PETG
「ポリエチレン・テレフタレート・グリコール(PETG)」は、強度・対薬品性・耐湿性に優れ、透明度が高い材料です。食品容器への利用も可能な安全性の高いグレードもあります。
ナイロン
「ナイロン(PA11やPA12など)」は、高い強度・耐久性・耐摩耗性・柔軟性を併せ持つ材料です。摺動部品やスナップフィット、機能的部品、治工具などの製作に適しています。
TPU/TPE
「熱可塑性ポリウレタン(TPU)」と「熱可塑性エラストマー(TPE)」は、ゴムのような柔軟性と弾力性を持ち、衝撃吸収性や振動減衰性にも優れる特徴的な材料です。スマートフォンのケース、ウェアラブルデバイス、緩衝材などに利用されています。
PC
「ポリカーボネート(PC)」は、極めて高い強度と耐衝撃性、良好な耐熱性を持つエンジニアリングプラスチックです。透明性にも優れており、自動車部品や高い安全性が求められる部品に適しています。
PP
「ポリプロピレン(PP)」は軽量で、優れた耐薬品性と耐疲労性、柔軟性を持つ材料です。ヒンジ構造や容器、自動車部品などに多く利用されています。
ASA
「アクリロニトリル・スチレン・アクリレート(ASA)」は、ABSに似た特性を持ちながら、耐候性(特に耐UV性)が大幅に向上している点が特徴です。屋外使用される部品に適しています。
高性能ポリマー
「高性能ポリマー(PEEK、PEKK、ULTEMなど)」は、非常に高い耐熱性、耐薬品性、機械的強度を持つスーパーエンジニアリング・プラスチックです。航空宇宙、医療、自動車などの要求の厳しい用途で使用されます。物性は魅力的なのですが、造形には高温対応の特殊な3Dプリンターが必要になります。
光硬化性樹脂には、以下のような材料があります。
標準レジン
「標準レジン」は、比較的安価な一般的な試作品製作向けの材料として活用されています。
エンジニアリングレジン
「エンジニアリングレジン」は、特定の機能を持つように開発されたレジンです。ABSやPPに似た高強度、靭性の材料、高耐熱レジン、TPUやシリコーンに似た柔軟性、弾性のある材料、ガラス繊維や炭素繊維を充填させた高剛性の複合材料などがあります。
キャスタブルレジン
「キャスタブルレジン」は、焼却時に灰残渣が少ない材料です。ジュエリーや精密部品のインベストメント鋳造用原型製作に多く使用されています。
デンタル・メディカルレジン
「デンタル・メディカルレジン」は、生体適合性認証(ISO 10993など)を取得している材料です。歯科模型、サージカルガイド、補聴器シェル、一時的な歯科補綴物、医療用モデルなどに使用されます。
セラミック充填レジン
「セラミック充填レジン」は、アルミナなどのセラミック粒子を高濃度に含有し、造形後に脱脂・焼結することでセラミック部品を製作できる材料です。
フルカラーレジン
「フルカラーレジン」はMJTによって複数の基本色レジンを混合して噴射することで、フルカラーの造形を可能にする材料です。
高い強度・剛性・耐久性の実現が可能になった「金属材料」
金属材料を利用した3Dプリンティングも、広く利用されるようになりました。金属材料は、高い強度、剛性、耐熱性、耐久性が特徴であり、造形方式や後処理(熱処理、HIP処理など)によって最終的な物性を改善できることが特徴です。このため、機能部品の製作に適しています。
3Dプリンターによって、複雑形状や内部に中空構造を持つ部品、ラティス構造による軽量化などが可能になったことで、その応用範囲が劇的に広がりました。3Dプリンターで造形可能な金属材料として、以下のような材料が挙がります(図4)。
図4 3Dプリンターで利用可能な金属材料とその特徴、代表的応用
ステンレス鋼
「ステンレス鋼(SUS316L, 17-4PHなど)」は、優れた強度、靭性、耐食性を持ち、比較的安価な材料です。産業機械部品、化学プラント向け部品、医療器具、装飾品などの幅広い用途に適用可能です。。
チタン合金
「チタン合金(Ti-6Al-4Vなど)」は、高い比強度(軽量かつ高強度)、優れた耐食性、生体適合性を持つ材料であり、航空宇宙部品、医療用インプラント(人工関節など)、高性能自動車部品に最適です。
アルミ合金
「アルミニウム合金(AlSi10Mgなど)」は、軽量で良好な熱伝導性を持つ材料です。自動車部品(特に軽量化が求められる部品)、航空宇宙部品、ヒートシンクなどに利用されています。
ニッケル超合金
「ニッケル基超合金(インコネルなど)」は、高温強度、耐酸化性、耐食性に極めて優れる材料です。航空宇宙エンジンの部品(タービンブレードなど)、発電用タービン部品、化学プラントなど過酷な環境で使用される部品の製作に適用されています。
工具鋼
「工具鋼(マルエージング鋼など)」は、高い硬度と耐摩耗性を持つ材料です。射出成形用金型、プレス金型、切削工具などの製作に用いられます。
銅・銅合金
「銅・銅合金」は、高い電気伝導性と熱伝導性を持つ材料です。電気・電子部品(コネクタ、ヒートシンク)、誘導コイル、ロケットエンジン部品などに利用されています。
貴金属
「貴金属(金、プラチナ、銀など)」も3Dプリンターで造形可能になりました。ジュエリーや特殊な産業用途向け部品の製作で利用されています。
過酷な環境で利用する製品の造形を可能にした「セラミックス材料」
セラミックス材料は、極めて高い硬度、耐熱性、耐摩耗性、耐食性を備えた材料です。加えて、その多くは優れた電気絶縁性を示します。また、熱伝導率や熱膨張率は材料により大きく異なるため、用途に応じた使い分けが重要になります。その一方で、靭性が低く脆い(割れやすい)という欠点があります(ジルコニアは例外的に高靭性)。これらの特異な物性から、特定の過酷な環境下で利用されています。3Dプリンターで造形可能なセラミックス材料には、以下のような材料があります(図5)。
図5 3Dプリンターで利用可能なセラミックス材料とその特徴、代表的応用
アルミナ
「アルミナ(Al2O3)」は、最も広く利用されているセラミックスの一つです。高い硬度、耐摩耗性、耐食性、優れた電気絶縁性を持ち、比較的安価な点が特徴です。産業機械部品、耐摩耗部品、電気絶縁部品、切削工具などに多く用いられています。
ジルコニア
「ジルコニア(ZrO2)」は、セラミックスの中で最も高い強度と靭性を持つ材料です。耐摩耗性、耐食性、生体適合性にも優れます。歯科用インプラント、人工関節、ナイフ、摺動部品などや宝飾品の材料として利用されます。
シリカ
「シリカ(SiO2)」は耐熱性、電気絶縁性に優れます。
窒化ケイ素
「窒化ケイ素(Si3N4)」は高温環境下での強度保持性に優れ、耐熱衝撃性も高い材料です。エンジン部品、ベアリング、タービン部品などに用いられています。
ハイドロキシアパタイト
「ハイドロキシアパタイト(HAp)」は、人骨の主成分に近い生体親和性の高い材料であり、骨補填材やインプラントコーティングに利用されます。
コーディエライト
「コーディエライト」は、熱膨張係数が非常に低く、耐熱衝撃性に優れる材料です。高精度が求められる半導体製造装置の構造部品や、天文・宇宙分野の光学部品などに用いられます。
これら以外にも、セラミックスに類似した材料として、ガラス材料やコンクリートなども3Dプリンターで造形可能になってきました。コンクリートを3Dプリンティングすることで、建築物や風力発電用のタワーを建設するといった試みが行われるようになりました。
RX Japan 合同会社では、日本最大級の製造業の展示会「ものづくり ワールド」を東京で行うほか、大阪・名古屋・福岡でも開催しております。
展示会場では、製造業の最先端事例や設計開発の最前線の話題が学べる併催セミナーも開催しています。
来場だけでなく展示会への出展も受け付けております。気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
●出展・来場に関する情報はこちら
高付加価値材料の適用による産業イノベーション
高付加価値材料の適用による産業イノベーション
特性のカスタマイズを可能にする「複合材料」
3Dプリンターに、さらに高付加価値な機能を備えた材料を活用できるようにするための技術開発が急速に進められています(図6)。高付加価値材料を利用した3Dプリンティングによって、応用先にイノベーションを創出する動きが活発化しています。
図6 3Dプリンター用材料の高付加価値化による応用拡大
既存の造形技術では加工が困難だった複合材料も、3Dプリンターを利用することによって、高精度で造形可能になってきました。複合材料は、母材となる樹脂などに強化材(主に繊維)を添加することで、特定の特性を向上させた材料です。母材となる樹脂の軽量性を維持しながら、強化材の種類・形状・量・母材中での分散性などを調整することで、要求に応じて強度、剛性、耐熱性などをカスタマイズさせながら向上させることができます。3Dプリンターで造形可能な複合材料として、以下のようなものがあります。
「繊維強化ポリマー(FRP)」は、熱可塑性樹脂(ナイロン、ABS、PLA、PEEKなど)を母材として、短繊維または連続繊維で強化した材料です。炭素繊維(カーボンファイバー)で強化すれば高い比強度・比剛性(軽量かつ高強度・高剛性)を実現可能であり、同時に導電性も発現します。一方、ガラス繊維(グラスファイバー)で強化すれば、良好な強度と剛性を炭素繊維より安価に実現可能であり、電気的には絶縁性となります。その他、ケブラー繊維で強化した高い耐衝撃性を持つ材料、金属基複合材料(MMC)やセラミックス基複合材料(CMC)も存在します。ただし、3Dプリンター用材料としての利用は、まだ限定的です。
造形前に複数種類の材料を複合化させた材料だけでなく、造形時に複数材料を組み合わせて適材適所に適用する技術の開発も進められています。こうした技術は、マルチマテリアル・プリンティングと呼ばれています。
生体組織とのインタフェースを可能にする「生体適合性材料」
利用者の利用目的や利用部位の形に個別対応する必要がある医療器具などの製作は、カスタム対応が可能な3Dプリンターの適用が最適な分野です。ただし、そこで利用する材料には、生体適合性(毒性がない、免疫反応を引き起こさない、細胞毒性がないなど)を備えていることが極めて重要になります。すでに、こうした要求に応える3Dプリンター用の生体適合性材料が多数用意されており、適切な機械的強度(骨代替なら骨に近い強度と弾性率)、滅菌処理への耐性、生体吸収性や生体活性(骨形成を促すなど)といった特徴を持つ材料もあります。3Dプリンターで造形可能な生体適合性材料として、以下のような樹脂、金属、セラミックスが利用されています。
「生体適合性樹脂」としては、金属の代替材料としても注目されているPEEKやPEKK、ナイロンや光硬化性樹脂などが提供されています。一方、「生体適合性金属」としては、チタンおよびチタン合金、特定のステンレス鋼、コバルトクロム合金などが、「生体適合性セラミックス」としてはジルコニア、アルミナ、ハイドロキシアパタイト、リン酸カルシウム系セラミックス、バイオアクティブガラスなどが利用可能です。
このうち、チタン合金や高性能ポリマー(PEEKなど)、あるいはジルコニアなどのセラミックスは、患者一人ひとりの解剖学的特徴に完全に適合する整形外科用(人工関節など)、歯科用、頭蓋顎顔面用のインプラントの作製に多用。手術時間の短縮、患者の回復促進、長期的な機能改善が期待されています。また、TPUやナイロンなどの柔らかいポリマー材料を用いて、患者の体型やニーズに合わせた義肢や装具を、従来よりも低コストかつ短期間で製作できるようにもなりました。これにより、患者のQOL(生活の質)向上が期待されています。
また、体内で徐々に分解・吸収される特徴を持つ「生体吸収性材料」の活用も広がっています。具体的には、PLA誘導体、ポリカプロラクトン(PCL)、ポリグリコール酸(PGA)などがあります。さらに、細胞を生きたまま3次元的に配置するバイオプリンティングに使用する「ハイドロゲル/バイオインク」と呼ぶ細胞を含むインク材料の活用にも注目が集まっています。これらの材料を用いて、組織や臓器の再生を目指す研究が活発化。再生医療や創薬研究の加速に貢献しています。
電気的・磁気的・光学的な機能を作り込む「機能性材料」
これまで3Dプリンターは、機械部品の製作や機器の筐体や自動車の内装など構造体の製作での利用が中心でした。これが現在、電気的、磁気的、光学的な機能を実現するデバイスの生産に3Dプリンターを適用する試みが増えてきました。導電性材料と絶縁性材料を組み合わせることで、回路パターン、センサー、アンテナ、その他の電子部品を、構造部品の内部や表面に直接形成する研究開発が進んでいます。これによって、ウェアラブルデバイス、IoTセンサー、カスタム電子機器などの小型化、高機能化、設計自由度の向上が期待されています。
まず、3Dプリンターで造形可能な導電性材料として、多様な導電性フィラーの利用が広がっています。カーボンブラック、グラファイト、カーボンナノチューブ(CNT)、金属粒子などを、ポリマー母材(PLA、ABS、TPUなど)に添加した複合材料です。また、導電性ペーストやインク(銀、銅など)を利用した塗布・印刷や純銅粉末を用いた金属3Dプリンティングの利用も広がっています。これらの材料は、電磁波シールド(EMIシールド)、静電気対策(ESD)が必要な治工具や部品、埋め込み型センサー(歪みセンサー、温度センサーなど)、アンテナ、簡易的な回路形成、ヒートシンクなどの製作に利用されています。
また、多様な絶縁性・誘電性材料も3Dプリンターで造形できます。多くの標準的なポリマー(ABS、PLA、PC、PEEK、PPSなど)やセラミックス(アルミナ、窒化ケイ素など)は、本来、良好な電気絶縁性を備えています。また、高周波用途向けには、誘電損失が小さい特殊な材料(変性PPEなど)も開発されています。すでに電子機器の筐体やハウジング、コネクター部品、高電圧用絶縁部品、基板材料、RF(高周波)部品(アンテナ基板、フィルターなど)、キャパシタ構造などの製作に利用されています。その他、セラミックスとポリマーの複合材料によって、誘電特性を制御する研究も行われています。
まとめ
まとめ
3Dプリンターで利用可能な材料が多様化・高度化することで、3Dプリンター用材料の市場は着実に成長しています。調査会社である矢野経済研究所は、3Dプリンター材料の世界市場規模(エンドユーザーの購入金額ベース)は、2023年に前年比24.9%増の4607億2000万円にまで達したと推計。今後、3Dプリンター本体の高性能化と材料開発がさらに進むことによって、少量もしくは中量生産の実用部品の生産への適用が加速していくものと予想しています。その結果、2023年から2028年にかけて年平均成長率(CAGR)17.3%で成長し、2028年には市場規模は1兆円を超えるとみています。
適用可能な材料のさらなる多様化と高度化に牽引されて、3Dプリンターの応用と利用シーンは一層拡大し、応用市場の規模も成長することは確実です。3Dプリンター用材料の進化はまだまだ始まったばかり。材料コスト、特性の均一性、特定プロセスで利用可能な材料の制限、リサイクル性など、依然として克服すべき課題も存在します。これらの課題を解決するための、高性能新素材の開発、マルチマテリアル・プリンティング技術、材料加工・プロセス制御技術の改善、リサイクル技術の開発などが活発に進められています。材料技術のブレークスルーと、その潜在能力を引き出す適用材料の特性に合致した造形技術の進歩は、製造業に大きなインパクトをもたらすイノベーションを生み出すことでしょう。
RX Japan 合同会社では、日本最大級の製造業の展示会「ものづくり ワールド」を東京で行うほか、大阪・名古屋・福岡でも開催しております。
展示会場では、製造業の最先端事例や設計開発の最前線の話題が学べる併催セミナーも開催しています。
来場だけでなく展示会への出展も受け付けております。気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
●出展・来場に関する情報はこちら
執筆者プロフィール
伊藤 元昭
富士通株式会社にて、半導体エンジニアとして、宇宙開発事業団(現JAXA)の委託による人工衛星用耐放射線半導体デバイスの開発に従事。日経BP社にて、日経マイクロデバイスおよび日経エレクトロニクスの記者、副編集長、日経BP半導体リサーチの編集長を歴任。
▼この記事をSNSでシェアする